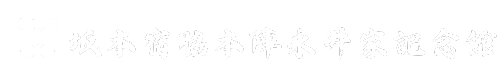2025/8/5
中山道坂本宿がどのような目的で作られ、それ以降どのように発展してきたかなど知らないことが 多くあり、坂本の地元で活動をしていらっしゃる、坂本歴史文化研究会代表の荒木典親さんをお招き
して、永井家記念館のスタッフ勉強会を開催しました。

45分程の座学では、中山道など五街道は徳川幕府の
軍事行動のために作られた街道であったこと。坂本宿は
東に碓氷関所、西に難所の碓氷峠があり、これらを通過
するための拠点の宿として、中山道では重要な宿場の
一つであったこと。
永井家の庭に今も流れている川は、400年前に坂本宿創設時から流れている生活のための用水
だったこと等、知らなかったことをいろいろ教えていただきました。
さて、休憩をとった後は、暑さ対策の水分補給をして坂本宿のフィールドワークです。
霧積川から水を引き入れ、往還の真ん中を流れていた用水(現在は片側に寄せられています)や
各家(北川・南側)の裏に流れている用水は、防火対策や牛馬手入れ、農業用水に使用されていて
今も当時と同じように流れていることに驚きます。


坂本宿下木戸で荒木さんから説明を受けるスタッフ
坂本宿の代表的な建屋、かぎや、米屋、佐藤本陣、坂本出身の俳諧師の小蓑庵碓嶺、書家の武居九夏に関連する家や、小林一茶、若山牧水が定宿として使っていた家などエピソードをまじえて説明をしていただきました。
最後に碓氷峠の森公園峠の湯の敷地内にある
縄文時代に使用されていた祭祀に使用されたと思われる
遺跡見学。「縄文時代に坂本の地でも、集落があった
ということを証明しています」とのお話。
縄文人はどのような思いを託して祭祀を行ったのでしょうか。
遠い過去へ思いをはせます。

猛暑の中、快く講師のお話を受けてくださった荒木さんにあらためて感謝するとともに、スタッフの皆さんお疲れさまでした。
これからも、坂本宿の歴史を勉強してまいりましょう。