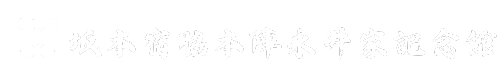館長ご挨拶
ご挨拶
私は、永井家の長女として生まれ、坂本の山や川を友とし、育ちました。
祖母ちよは、季節の変わり目になると幼い私に、陶器や漆器などの手入れの方法を教えてくれ、「大切に残すのですよ。」と語り、木製の水受け台を見ながら、「これは、この家にお越しくださった明治天皇がお使いになられたものですよ。」と永井家の歴史を話し、これらを後世に伝えることの重要性を諭してくれました。
祖夫一雄は、岩手大学の前身で日本最初の高校農林学校である盛岡高等農林学校を卒業し、群馬県の農林技師を経て満洲国の興農部技師として赴任し、終戦を待たずに日本に帰国しました。
戦後、農村の復興が祖国再建への道であり、坂本の復興にもつながると、寒冷地に適応した農業、農作物を見つけだそうと、当時としてはめずらしかったトマト、アスパラガス、イチゴなどの作物を育てていてましたが、その祖父の願いもかないませんでした。
高祖父善太郎・曾祖父延次郎は、坂本の戸長や町長を務め、経済発展のため養蚕にも取り組み、坂本の人々と共に坂本小学校の設立に協力し、小学校が類焼した時には、自宅の一部を教室として提供しました。
また、キリスト教徒としても熱心に活動し、この家に基督教講義所を開設し、1903年(明治36年)から1926年(大正15年)までキリスト教日曜学校も開講していました。祖夫一雄の葬儀時には、門の外にまであふれる方々が、声高々と誇らしそうに讃美歌を歌う姿を、当時9歳だった私は、言い知れぬ感動と驚きをもって見ていたことを、今でもはっきりと覚えております。
明治維新以降、前向きで新しい世界観、教育、経済の立て直し、平和、自由、平等を目指し、生き生きと生きたきた原動力は、この新島襄を代表とするキリスト教の教えが大きな要因であると考えています。
心の教育や誇りを、今この時代だからこそ伝え、残していきたいと思います。
母綾子は、新聞取材時、「古い家を守る事は、大変。しかし守ることは、脇本陣に生まれた者の役目。」と語り、古文書を地元の有志の方と調べた父憲作の資料には、「当時、脇本陣で使用したと思われる屏風、襖、書画、骨董や陶器が家族の努力によって保存されている。
すでに本陣がなくなった今、この貴重な品々によって坂本宿の様子や文化を知ることができる。江戸時代から明治初期にかけて坂本宿では、農村とはまったく異なった高度の文明であったことが知られる。」と記しています。
こうした過去からの永遠の命や思いは消えることはありません。先人たちの、坂本宿を守りたい。脇本陣を守りたい。との思いが、建物と品々という形で残されています。
これらの思いを、坂本宿脇本陣永井家記念館として後世に残し続けたいと強く思いました。
その時代と共に、過去の見えない心にまで触れたいただければ幸いと存じます。
坂本宿脇本陣永井家記念館館長
善如寺 留美子